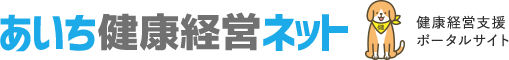学校法人東海学園 東海学園大学
ガッコウホウジントウカイガクエン トウカイガクエンダイガク
- 101~300人
- 医療法人/サービス業
| 所在地 | 〒470-0207 愛知県みよし市福谷町西ノ洞21番地233 |
|---|---|
| URL | https://www.tokaigakuen-u.ac.jp/ |
| 社員数 | 179名 |
| 業種 | 医療法人/サービス業 |
- 業務内容
- 学校法人東海学園は1888年浄土宗学愛知支校を起源とする学校法人です。東海学園大学は1995年に設立され、みよし市と名古屋市に6学部・1大学院を擁する私立大学です。開学以来、人は皆まわりの人々や社会・自然環境に生かされ、生きていくという考え方「共生(ともいき)」が本学の教育の理念です。
その理念に基づいた「ともいき教養教育」をはじめ、各学部で1年次からゼミを導入し学びの基礎を育み、学びの理解を深め、専門性を身に付けていく教育により、社会で活躍する人材育成を目指しています。
6学部の内、名称に『健康』を冠する2学部(健康栄養学部・スポーツ健康科学部)が中心となり、「食」や「運動」に関する様々な取り組みを地域の皆さまに展開することで、『健康増進』の普及に努めています。
健康経営に関する
自社のセールスポイント

“東海学園大学は健康を大切にしている大学です”
本学は開学以来、“健康を大切にする教育”を継続してきた。現在、名称に”健康”を冠する2学部(健康栄養学部、スポーツ健康科学部)を中心に、「食」や「運動」に関する様々な教育活動を行っている。
健康に重点をおいた教育実践に加え、2023年度には産業医でもある学長が就任し、学長自ら『健康経営宣言』を発した。教職員や学生の健康を“重点項目”と位置づけ、一人ひとりが健康増進を意識し、心身ともに健康で生き生きと学び・働くことができるよう取り組みを開始した。
なお、本学の『健康経営宣言』の特色は、教職員や学生だけでなく、「地域の皆さま」を対象にした事業を通しての『健康増進活動』の普及促進にある。
企業に比べ、大学などの教育機関では『健康経営』があまり浸透していないが、本学では長年培ってきた“健康を大切にする教育”を実践しつつ、教職員の健康のみならず、地域の社会貢献活動としての『健康経営』を積極的に推進している。
すべて開く閉じる
取組状況について
食生活の改善
-
- 期間
- 2000年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・全教職員の健康診断時や大学祭で、手掌をセンサーに当てるだけで推定野菜摂取量を測定できる“ベジチェック®”を導入した。また、ポスターを掲示し、毎日350gの野菜摂取を推進している。
・ヘルスリテラシー教育や教職員・学生の食生活改善のための施策として、食堂出入り口に健康栄養学部作成の食に関するパネルを設置した。
・事務局・非常勤講師室に野菜を使ったレシピのチラシを設置した。
・大学ウェブサイトの『健康経営』ページに、毎月1回栄養に関する記事を掲載している。
・さらに、健康栄養学部では、食生活・栄養・運動と健康に関する講義や実習を通して一人ひとりの健康増進を目指す『健康栄養プラザ』も開催している。
-
- 取組に対する成果
- ・現代人が抱える食生活の問題として、朝食欠食、栄養バランスの乱れ、塩分の過剰摂取、野菜不足などが挙げられるが、本学の教職員を対象にしたアンケート調査では、朝食を抜くことが週に3回以上ある人は、2023年度は16.7%であったが、2024年度は7.9%に減少した。
・また、主食・主菜・副菜をそろえて食べる日が2回/日以上ある日が1週間に1日もない人が9.0%から5.3%に減少した。
・さらに、うす味を心がけている/どちらかと言えば心がけているという人は、57.4%から67.6%に増加した。
-
- 工夫したところ
- ・健康診断という自らの健康を意識する時に野菜の摂取量を簡易的に測定することで、野菜の摂取を促進した。
・野菜の摂取を促すチラシを毎日出勤すると目に入る場所に設置し、自由に持ち帰ることができるようにした。
・食堂の出入り口に“食のパネル”を置き、栄養情報の提供を行うことで、野菜摂取を促した。
・大学ウェブサイトの『健康経営』ページに毎月1回栄養に関する記事を掲載した際には、同時にメール配信も行うことにより周知している。
運動機会の促進
-
- 期間
- 2000年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・“階段利用のススメ”として、キャンパス内の全階段、10段毎に“10段1キロカロリー減”のステッカーを貼付し、同じくキャンパス内の全エレベーター内に、階段昇降により得られる効果などについてのポスターを掲示することにより、階段の利用を促進している。
・三好キャンパスでは、各階、各踊り場にも“消費カロリー数”を表示した。
・教職員向けのストレッチ教室やヨガ教室、ゴルフ大会などを開催した。
・大学ウェブサイトの『健康経営』ページにスポーツ・運動に関する記事を掲載している。
・健康増進に関するポスターコンテストを行い、啓発活動を行った。
・また、スポーツ健康科学部では、学部行事として“とうがく競技祭”を実施しており、教職員も学生とともに古代スタディオン走などに出場している。
・スポーツ健康科学部のゼミナールでは、東海学園大学の教育の理念である「共生(ともいき)」をテーマに、“地域の健康づくり”にも寄与できるよう『ともいき体操』を制作し、活動を行っている。
-
- 取組に対する成果
- ・ヘルスリテラシー教育のひとつとして、ステッカーやポスターなどの掲示物を利用し、階段使用を促進したことにより、本学において教職員を対象にしたアンケート調査では、教職員のうち階段を利用していない人は、2023年度は17.4%であったが、2024年度は13.2%に減少した。
・三好キャンパスではお昼の休憩時間に食後の運動として階段昇降を始めた職員もいる。
・ストレッチ教室後には、「ストレッチ、楽しかった。」「ストレッチ前後で比較するのが良かった。」「腰痛ストレッチを続けます!」などのコメントが得られた。
・ゴルフ大会については健康経営に携わるメンバー以外からの申し出であり、教職員が自ら運動機会の促進に向けて活動した。
-
- 工夫したところ
- ・日頃階段を利用している人には継続できるように階段に、日頃階段を利用していない人には階段昇降を勧めるためにエレベーター内に、ポスターを掲示した。
・三好キャンパスでは、階段昇降のモチベーション維持のために各階・各踊り場にも消費カロリー数を表示した。
・教職員向けのスポーツ・運動教室については事前にアンケート調査を行い、希望が多かったストレッチ教室とヨガ教室を開催した。
・大学ウェブサイトの『健康経営』ページにスポーツ・運動に関する記事を掲載するだけでなく、全教職員にメール配信も行った。
・健康増進に関するポスターコンテストでは、健康の三要素のひとつである運動についてを題材にしたポスターが受賞するなど、学生とともに取り組んでいる。
他の企業等への健康経営の普及促進
-
- 期間
- 2000年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・「運動機会の促進」「食生活の改善」を図るため、地域の皆さまに対して以下の事業を積極的に展開し、『健康増進活動』の普及促進に努めている。
・官学連携による地域住民の健康増進として、キャンパスがある名古屋市とみよし市で『なごや健康カレッジ』および『みよしフレイル教室』実施した。
・各自治体と共同して市民向けの健康増進体操『よしよし体操/みよし市』、『木曽の大桑ほこっと体操/長野県大桑村』を制作し、各種市政イベント等で普及活動を行っている。
・本学オリジナルとして作成した健康体操『ともいき体操』は、学内のみならず健康増進等の地域連携活動の際のエクササイズとして活用されている。
・健康栄養学部では、名古屋キャンパスの施設を開放して近隣住民を対象とした栄養教室や食への関心を高めるための『健康栄養プラザ』を実施している。
・大学ウェブサイトに『健康経営』のページを設け、食生活の改善、運動機会の促進など健康増進にかかる情報発信について、学外に向けて積極的に行っている。
-
- 取組に対する成果
- ・『木曽の大桑ほこっと体操』については、長野県大桑村の方々の健康増進に寄与したと評価されて、『令和5年長野県知事賞』を受賞した。
・2024年度の『なごや健康カレッジ』では、運動をある程度している参加者でも、体調が「良くなった」と回答した割合が約半数おり、「脚の筋力が強くなった感じがするなど」のコメントが複数挙げられた。参加全員が「楽しい」か「どちらかといえば楽しい」と回答し高い満足度となった。
・『健康栄養プラザ』では、参加者アンケートでは、「大変勉強になった」「子どもが野菜について興味をもつことができた」「また食生活についての企画をしてほしい」「参加者同士の情報交換ができ良かった」等の評価を得ている。
-
- 工夫したところ
- ・『なごや健康カレッジ』では、参加者の体力的な面を考慮し、2024年度からは65歳以上から60歳以上に変更した。
・『ともいき体操』については、大学ウェブサイトの『健康経営』のページから動画視聴できるようにし、広く普及に努めた。
・健康増進体操の制作にあたっては、“誰でもできる、簡単で楽しい”体操に努めた。
・『健康栄養プラザ』では、大学教員はじめ、各テーマの専門家が、「飲み込みやすい食事」や「野菜を食べよう」、「みその再発見」といった“子どもから大人まで”楽しめる身近な話題を、アカデミックな視点で伝えている。
受診勧奨の取組
-
- 期間
- 2000年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・学生の健康診断に加え、教職員の健康診断をキャンパス内で年1回実施し、全教職員の受診の徹底を呼び掛けてきた。
・2023年5月『健康経営宣言』後は、受診率100%を目指して呼びかけ等を徹底している。
・各キャンパスで、年に1回実施している教職員の健康診断を案内するメール配信時に全員受診を呼びかけ、また当日受診できない場合は各自で人間ドック(私学共済の補助あり)を利用するなど必ず受診するよう呼びかけている。
・個人で人間ドック受診の場合は保健室への健診結果提出を求め、全教職員の健康状態を把握している。
-
- 取組に対する成果
- ・2023年度は、1名のみが未受診であった。これを踏まえて、2024年度は、9月より毎月受診勧奨の連絡を行ったことにより、対象者全員が受診する見込みとなっている。
-
- 工夫したところ
- ・勤務時間内に校内で受診できるようにした。定期健康診断の日程は2日間とし、A日程で健診を受けることが出来ない者は、B日程で受けることが出来るよう配慮した。さらに契約した健診業者の施設で、1か月間は無料(雇用主負担)で受診できる期間を設けた。
・全員受診に繋がるよう、学外受診希望者へは、担当部署だけでなく衛生委員からも受診勧奨メールを発信した。また、受診が済んでいない個人に、受診を促す電話・メールで呼びかけを複数回行った。
健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定
-
- 期間
- 2000年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・学長および学長補佐(両者とも産業医資格あり)を始め、事務局長、総務・広報担当、保健室スタッフ(保健師・看護師資格あり)、健康栄養学部長で構成される『健康経営プロジェクトチーム』(総勢11~12名)を立ち上げ、年度ごとの『健康経営実施計画』を作成している。
-
- 取組に対する成果
- ・年度ごとの『健康経営実施計画』の作成にあたっては、具体的な実施内容に加えて担当を明確にし、健康増進や働き方改革の推進を図ることができた。
・特に2024年度の計画策定にあたっては、2023年度のアンケート結果の分析および実施内容の振り返りを行い、必要な点を改善することができた。
-
- 工夫したところ
- ・『健康経営実施計画』については、学内の衛生委員会においても共有し、内容について審議したうえで、産業医や保健室スタッフ、人事担当部署等と連携を取りながら確実に実施するよう努めた。
・年間の『健康経営実施計画』を決めるに当たっては、全教職員を対象にした“健康経営アンケート”の結果を反映させることで、より有意義な計画・活動になるように努めた。
産業医または保健師が健康保持・増進の立案・検討に関与
-
- 期間
- 2000年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・『健康増進計画』の立案等については、衛生委員会のメンバーである産業医・保健室に配置した看護師・保健師のアドバイスを得ながら、委員会として活発な議論を行っている。
・具体的には、毎月の職場巡視で産業医からアドバイスを得るほか、定期健康診断時、オプションで検査項目を増やすなど、産業医と相談しながら健康診断を実施している。
-
- 取組に対する成果
- ・衛生委員会とは別に、健康経営の具体的な運用を担う組織として『健康経営プロジェクトチーム』を立ち上げ、健康保持・増進の立案・検討を行っている。同チームのメンバーには学長および健康経営担当の学長補佐(両者とも産業医有資格者)、保健師、看護師、総務部長(働き方改革担当)も参加している。
・大学ウェブサイト上の『健康経営』のページでは、在職の教職員でもある産業医・保健師・看護師らが自ら記事を書いて情報発信しているが、「親しみやすく読みやすい内容である」と好評であった。
-
- 工夫したところ
- 「衛生委員会」及び『健康経営プロジェクトチーム』は学内メールシステムを利用し、情報共有を図り意見交換をしながらプロジェクトを進めた。
管理職及び一般社員それぞれに対する教育
-
- 期間
- 2000年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・毎年度1回全教職員対象のFD・SD研修会とハラスメント防止対策研修会をそれぞれ実施している。
・2021年度からは毎年度1回、外部講師を招き事務職員の職階別にコミュニケーション能力などテーマを設け研修会を実施している。
・2023年5月『健康経営宣言』後は、更なる“職員教育”に力を注いでおり、2023年度のFD・SD研修会では産業医の資格を有する学長が健康経営について講話を実施した。
-
- 取組に対する成果
- ・教職員を対象にした通常の研修会に加え、メール配信やホームページによる啓発活動、ポスターの掲示やデジタルサイネージによる広報など、あらゆる媒体を活用して教育をすることができた。
-
- 工夫したところ
- ・健康経営に関する重要事項(例 食の改善・運動機会の必要性、喫煙の健康被害等)について、全教職員宛にメール配信をするとともに、ホームページや学内ポスターなど、考えられる媒体全てを使って周知を図った。
・学長や健康経営担当の学長補佐が医師であることから、様々な機会を通じて情報発信することで、全教職員の“健康に対する意識改革”に努めた。
・全教職員向けのアンケートを2023・2024年度に実施し、その結果や動向について教授会等で周知するとともに、次年度の活動の参考にした。
・生命保険会社との間で健康経営にかかる協定を締結することで、同社発行の健康に関する情報誌を配布等できるようにしたり、健康診断やイベント時には啓発機材等の借用ができるよう工夫した。
適切な働き方の実現
-
- 期間
- 2000年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・2019年4月に施行の“働き方改革”に沿って、職員の意識改革に努めてきている。
・育児・介護休業の制度や特別休暇の制度等を整え、“仕事と家庭の両立“ができるよう努めている。
・2023年5月『健康経営宣言』後は、より適切な『ワークライフバランス』の実現に向けて、更なる“運営改善”に努めている。
-
- 取組に対する成果
- ・職員の時間外勤務については、2022年度は平均して一人につき年間72.7時間あったが、2023年度は59時間となり前年度より減少した。
・有給休暇の取得については、2022年度には平均して一人につき年間8.02日だったが、2023年度は10.67日となり前年度より増加した。
-
- 工夫したところ
- ・教職員の負担軽減を図るために、それまで殆ど対面式で行われていた会議や各種委員会について、可能なものは“リモート会議”や“メール会議”での開催に改めるとともに、電子データ資料の活用に徹底した。これらの改善により、移動時間の短縮や事務の簡素化を果たすことができた。
・「仕事」と「プライベート」を両立させることで、働きやすい環境を作り、職員各自の能力を十分に発揮できるよう、加えて健康維持に努めることを目的に、事務職員については2023年8月から毎週金曜日を“ノー残業デー”とし、定時退勤を推奨する活動を展開した。
・年2回、期間(8月~9月、2月~3月)を定めて“有給休暇取得推進期間“と定め、職員が休暇を取りやすい職場環境の醸成に努めた。
・“ノー残業デー”促進ポスターを各部署に掲示し、定時退勤しやすい雰囲気の醸成に努めた。
コミュニケーションの促進
-
- 期間
- 2000年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・本学は2つのキャンパスがあるが、入学式・卒業式・入試・オープンキャンパス、研修会など、部署の枠を超えて全員で業務の機会も多く、意思疎通を図っている。
・各学部の教授会に事務局員が参加するなど、教員・職員間での連絡を取り合っている。
・事務局においてはデスクの配置を工夫し、コミュニケーションがとりやすいようにしている。
・また、コミュニケーションの不足が原因の一つと考えられるハラスメントに対しては防止対策研修会などを行い、グループワークも実施している。
・大学ウェブサイトの『健康経営』ページにコミュニケーションの重要性についての記事を掲載した。
-
- 取組に対する成果
- ・本学は2つのキャンパス、6学部、教員・職員など、円滑なコミュニケーションが取りにくい状況であるにも関わらず、教職員を対象にしたアンケート調査では、学部内や部署内でのコミュニケーションは十分とれている/まあ取れているという人が2023年度は77.4%、2024年度は71.5%と、ともに7割を超えていた。
-
- 工夫したところ
- ・上司と部下のコミュニケーション不足はストレス要因になり得る。現学長は各学部の教授会に出席し、また、役職教員との面談を行なっている。事務局では、上司と部下の面談を継続的に行なっている。
・教職員、嘱託職員、誰もが参加できるストレッチ教室やヨガ教室、ゴルフ会、リラクゼーション教室などを開催した。
治療と仕事の両立支援
-
- 期間
- 2000年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・業務外の傷病により欠勤が3か月を超えた場合は1年6か月以内で休職できるよう就業規則に定めている。同時に、生活面の心配なく治療に専念できるよう私学共済に傷病手当金を申請し、給付を受けることができる。
・午前休・午後休と半日有給休暇を取得できるため、休暇取得による通院治療は現状でも可能であるが、今後時間単位の休暇取得が可能となるよう、制度整備や必要なシステム整備等を進める。
-
- 取組に対する成果
- ・休職者が円滑に職場復帰できるよう、新たに『職場復帰の手引き』を定め、主治医や産業医と連携を取りながら、“休業中のケア”や“職場復帰後のフォローアップ”ができる体制を作ることができた。
・休暇取得システムの改修を進め、2025年度からは時間単位で有給休暇が取得できるようになる。このことにより、治療のための通院等がし易くなり、治療と仕事の両立支援に大きく寄与できるよう前進した。
・育児・介護休暇に関する規則を改正し、2025年度からは子の看護休暇の取得事由範囲を拡大するとともに、給与の取扱いについては「有給」での取得ができるよう規則を改めた。
-
- 工夫したところ
- ・職員が療養・通院をよりし易くなるよう、新たな時間単位の休暇取得の導入に加え、事務手続きについても簡略化した。具体的には、例えばインフルエンザでの自宅療養に際してはこれまで必要としていた医師の診断書の提出を不要とし、治療・療養がし易い体制を整える工夫をした。
保健指導の実施
-
- 期間
- 2000年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・予約制で産業医・学校医から保健指導をうけるこができるようになっている。
保健室の看護師・保健師は、産業医・学校医の指示のもと、必要と思われる人に保健指導を行っている。
・2023年5月『健康経営宣言』後は、更なる充実に努めている。
・キャンパス毎の保健室に血圧計を設置して気軽に相談や指導を受けられる体制になっているが、さらに気軽に血圧測定ができるよう、保健室以外の他の場所にも血圧計を追加設置している。
・定期健康診断の結果をもとに、保健室で保健指導を行うとともに、予約制で産業医・学校医の保健指導をうけることもできるようになっている。
-
- 取組に対する成果
- ・学校医・産業医の保健指導を受けた者は、2024年度は約200名中6名であった。
・学校医・産業医の指示のもと、看護師・保健師の保健師指導を受けた者は、2024年度は約200名中51名であった。
・病院へ行くまではないが医師に相談したいと望む人から面談設定は好評であり、面談を行ったことで、早期の治療開始や生活習慣改善につながっている。
・継続的に保健指導が必要な教職員には、看護師・保健師が定期的な保健指導を継続している。
-
- 工夫したところ
- ・定期健康診断の全体の結果は、メールにて対象者全員へ報告し、健康意識が上がるよう工夫した。
・定期健康診断対象項目で、すべてがA判定、または1つのみB判定であったものには、保健室作成の表彰状をおくり、全体の健康意識を上げるよう努めた。
・産業医による保健指導は希望者だけではなく、緊急性のある場合は早々に面談の場をもうけた。
・看護師・保健師による保健指導は、その場限りにならないよう、継続した保健指導を心掛けている。
禁煙対策
-
- 期間
- 2000年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・開学当時から禁煙指導を開始し、2003年5月の健康増進法施行により、敷地内指定場所以外の禁煙指導を徹底した。
・以降、喫煙可能場所を順次縮小するとともに、2014年度からは毎月7・17・27日を『環境美化・禁煙デー』と位置付け、敷地内に幟を立てて学内巡回をしてきた。
・2023年5月『健康経営宣言』後は教職員・学生に分煙マナーを徹底し、“喫煙と健康被害”を周知している。2024年4月からの「敷地内全面禁煙」をめざし、学内における関係委員会等で具体策の検討を進めた。
・敷地内に禁煙に関するポスター・看板を掲示した。
・FD(Faculty Development)・SD(Staff Development)研修会で学長が『健康経営宣言』を行うとともに、禁煙についての講話を行った。
・大学ウェブサイトの『健康経営』のページに“禁煙について”や“たばこの害について”の記事を掲載した。
-
- 取組に対する成果
- ・『健康経営宣言』および禁煙対策活動の開始をきっかけに、禁煙にチャレンジして継続成功している教職員が存在し、効果があった。
・全教職員を対象にしたアンケートでは、「現在喫煙している」と回答した教職員の数は、2023年度は15人だったが、2024年度アンケートでは5人となり、禁煙対策活動の成果がアンケートの数値にも表れている。
-
- 工夫したところ
- ・両キャンパスの教職員で構成された『禁煙対策チーム』を立ち上げ、各キャンパスの実情に即した禁煙対策活動を図ることができた。
・2023年度においては、学生を募集した『敷地内禁煙ポスターコンテスト』を実施し、優秀者のポスターを学内に掲示することで、職場内における禁煙のムードを高めることができた。
・さらに愛知県のポスターを掲示するとともに、学内のデジタルサイネージを活用し、たばこの害や禁煙の必要性について啓発を図った。また、教職員・学生が協働して幟(のぼり)を立てて学内を巡り歩く周知活動を続けたことにより、禁煙のムードやマナー向上の気運を高めることに努めた。
・学内のコンビニエンスストア経営者と折衝し、タバコの販売を取りやめることで、喫煙しにくい環境づくりに努めた。
従業員の感染症予防
-
- 期間
- 2000年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・インフルエンザの予防接種を勤務時間中に各キャンパス内で接種できるよう、事前予約をした希望者に有料で実施している。個人負担の一部を大学が補助し、負担軽減も図っている。
・新型コロナワクチンの予防接種を受けた場合、2日間(接種を受ける日・予防接種の副反応が見られた日)について、特別休暇(有給)を設定している。
・新型コロナウイルスの感染拡大を機に設置した、建物入り口の「アルコール手指消毒液」、各手洗いの「泡ハンドソープ」についてはそのまま残したうえで、手洗いの重要性については引き続き啓発している。
・新型コロナウイルスに備えて設置した窓口等のアクリル板の仕切りについては、新型コロナウイルスが第5類に移行したことにより一旦撤去したが、今後の感染状況に備えて現在は倉庫に保管し、必要に応じて設置できる体制になっている。
-
- 取組に対する成果
- ・学内でインフルエンザの予防接種を実施したことで、気軽に受けることが出来たと好評であった。
・新型コロナワクチン予防接種に関する休暇措置は、接種後発熱等の副反応がみられた者にとって、気兼ねなく休むことが出来たと好評であった。
-
- 工夫したところ
- ・新型コロナウイルスやインフルエンザなどについて、流行の兆しがみられるときは、「感染症サーベランス」を一斉メールし、状況の周知に努めるとともに注意を促した。
・インフルエンザなどでの自宅療養に際しては、これまで必要としていた医師の診断書の提出を不要とし、事務の簡素化をすることで治療・療養がし易い体制を整えた。
・新型コロナウイルスの予防接種が受けやすいよう、また副反応にも対応できるよう、新たに特別休暇の対象に加えた。
長時間労働への対策
-
- 期間
- 2000年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・36協定を基に、出退勤時間をタイムカードで管理し、超過勤務についても把握可能なシステムを導入し、管理者がいつでも確認できるようにしている。
・週40時間勤務とするため、土曜勤務者は原則その週に振替休日を前もって取得するものとし、当番制の18時まで勤務者は当日9時50分出勤で対応するなど、一部フレックス制を導入し、実質労働時間削減に努めている。入試等で日曜・祝日に出勤した際は振替休日を各自計画的に取得するよう推進している。
・実際に長時間労働が認められる職員に対しては、所属長面談において聞き取り等を行うことで、長時間労働職員の負担軽減対策等を図っている。
-
- 取組に対する成果
- ・毎週金曜日を“ノー残業デー”にしてから以降は、特に事務職員における時間外労働時間が大幅に減っており、大きな成果があった。
(時間外勤務実績:三好キャンパス:56%減、名古屋キャンパス:26%減)
-
- 工夫したところ
- ・各課内の目に付く場所に“ノー残業デー”の手作りポスターを掲出し、教職員の意識改革に努めた。
・各課の管理職が参加する事務局会議(月1回実施)において“ノー残業デー”や“有給休暇取得推進期間“の意義や留意点をその都度説明し、形骸化しないよう、職場環境の醸成に努めている。
・休務日に出勤した場合の振替休日の取得については、繁忙期を視野に入れて計画的に確実に取得するよう、事務局会議等で繰り返し周知している。
メンタルヘルス不調者への対応
-
- 期間
- 2000年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・毎年度1回、健康診断時に合わせストレスチェックを実施している。
・メンタルヘルス不調者より相談があった場合、私学共済や公的機関等の窓口を紹介している。
・学内に設置の学生相談室においてカウンセラーへの相談が可能だが、より相談しやすくなるよう、外部に教職員専用カウンセラーを置くことを準備中である。
・各部署の職員から「職務状況調査表」を提出してもらい、それを元に上長との面談を年に2回実施しており、メンタルヘルスに不調をきたしても早期発見できる体制をとっている。
・厚生労働省の「復職支援の手引き」をもとに、本学に合わせた「復職支援の手引き」を作成した。休職者が出た場合の対応に備えた。
-
- 取組に対する成果
- ・ストレスチェックを行うことにより、職場・職種分析ができ、両キャンパスごとの仕事の比重差を見直すきっかけとなった。
・ストレスチェックによる高ストレス者と、産業医との面談を行うことができた。
・保健室にはメンタルに関する相談が寄せられているが、早期に受診勧奨等の対応が出来たことで、休職等に至らずに済んだ事例があった。
-
- 工夫したところ
- ・本学の就業規則にあわせた、「復職支援の手引き」を作成した。
・保健室配置の看護師・保健師は、メンタル不調の相談はデリケートな内容を含むことを理解したうえで、医療知識を活かし、気軽に安心して相談をして頂けるよう心掛けている。
女性の健康保持・増進に向けた取組
-
- 期間
- 2000年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・教職員健康診断の血液検査項目に婦人科領域で最も多用されている腫瘍マーカーであるCA−125を加えている。
・育児休業がとりやすい体制を整え、加えて、育児休業後に出勤の際は、所定労働時間内で6時間を下回らない範囲内及び30分単位で短縮可能な育児短時間勤務が可能としている。
・女性の健康に関しては、月経、妊娠、出産、更年期障害、女性特有の疾患における課題などがあるが、男性のみならず女性自身の知識不足も課題とされている。ストレッチ教室、ヨガ教室を開催する際に、“女性のライフサイクルと健康”をテーマに、女性を取り巻く社会環境、女性の健康課題などについて健康セミナーDVDを上映した。
・大学ウェブサイトの『健康経営』ページに更年期、エクオール、子宮頸がん、乳がんについての記事を掲載した。
-
- 取組に対する成果
- ・本学において教職員を対象にしたアンケート調査では、女性の健康課題について、「関心がある/どちらかといえば関心がある」という人は、2023年度は76.3%だったが、2024年度は79.5%へ増加した。
-
- 工夫したところ
- ・教職員健康診断の血液検査項目に、卵巣がん、子宮内膜症などで陽性率が高くなるCA−125を加えている。
・大学ウェブサイトの『健康経営』ページでの発信、健康セミナーとして女性の健康について取り上げることで、リテラシーの向上に繋がった。