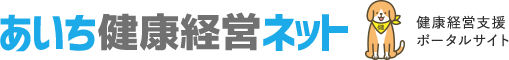株式会社服部商会
カブシキガイシャハットリショウカイ
- 1~30人
- 卸売業
| 所在地 | 〒496-0019 愛知県津島市百島町字三正六歩23 |
|---|---|
| URL | https://hattoris.co.jp/ |
| 社員数 | 29名 |
| 業種 | 卸売業 |
- 業務内容
- 地域産業に密着したNC工作機械・工具の総合商社。
ものづくりに欠かせない高性能な切削工具からツーリング・伝導機器・工作機器など1976年創業以来変わらない信頼の商品をお客様のニーズに合わせ真心を込めて提供。また、技術向上のベストアドバイザーとして的確かつ迅速な対応をする企業を目指します。
健康経営に関する
自社のセールスポイント

弊社には、創業以来「従業員の笑顔が私達の喜び」という想いが根底を流れております。
そんな想いと重なり、2017年頃の人手不足が深刻化する最中に健康経営の取り組みを始めました。
「従業員一人ひとりが精神的・経済的・身体的 全てにおいて幸せであること=Wellbeing」を目指す事こそが、企業としての最大の社会貢献であり企業価値を高めるものであるという信念は、健康経営推進の経験と知識が深まるにつれ強くなっています。
これまでの弊社の取り組みが評価され、健康経営優良法人2023ブライト500にも3年連続で認定されました。
今後も心のケアやワークエンゲージメント向上に努め、「仕事が楽しい」「仕事のやりがいを感じられる」健全な職場環境を整えることにより、生産性・業績だけではなく従業員と家族のWellbeingに重きを置いた「健康経営」を推進し、活気あふれる企業づくりに励んで参ります。
すべて開く閉じる
取組状況について
管理職及び一般社員それぞれに対する教育
-
- 期間
- 2017年10月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①健康をテーマとした情報提供の徹底
・全社員に社内チャットで、アクサ生命の『健康ワンポイントアドバイス』配信
・重要な内容は資料を作成して、朝礼や会議などでプレゼンテーションの開催
②全社を対象に充実した社内研修を実施
・年に2回、健康習慣アンケートを実施し、その結果をもとに各種健康セミナーの開催
・外部のエキスパートアドバイザーによる、ヘルスリテラシー向上をテーマにしたセミナーを実施
・産業医による、健診結果の見方や検査の必要性、有所見者に対する産業医との個人面談、禁煙セミナー/女性セミナー/歯科衛生士による、歯周病が全身に及ぼす影響についての講義等を実施
③管理職に対しての社内研修の実施
・外部のエキスパートアドバイザーに、健康経営の重要性をテーマに研修を依頼
④食生活の改善に向け調理の体験のイベントの実施
・全社員に栄養満点の豚汁の調理体験を実施
-
- 取組に対する成果
- ・定期的な情報提供により、社員間のコミュニケーションに健康に関する話題が増えました。健康管理の必要性を認識していただき、ヘルスリテラシーの向上となりました。
・産業医の方からの健康診断の助言をいただいたり、有所見者への直接の面談をしていただいたことで、自身の健康状態の改善度合いに対する意識・関心が向上されました。
・健康経営の本質的な考え方や支援の実務を習得し、チームとして実践支援するという目的をもって資格取得を奨励しました。その結果、健康経営アドバイザーを8名、エキスパートアドバイザーを1名が取得しました。
-
- 工夫したところ
- ・精神的・経済的・身体的 全てにおいて幸せであることの重要性を認識できるセミナーを実施しています。
メンタルヘルス対策としては、ストレスチェックを年に1度行い、その後のフォローとして、社内外の相談窓口のご案内を全社員に配布しております。また、体力テストも年に1度開催しており運動機会のきっかけ作りや社員間のコミュニケーション溢れる良いイベントとなっております。
・外部に『健康習慣アンケート』を依頼し、全国平均との比較や定量的な分析を行うことによって、今後のセミナー開催の内容や施策への落とし込みをしております。また、アンケートをもとにセミナーを行うことで、現状把握や意識向上を目的とした取り組みを行っております。
・Well-being経営を目指していくためには、ただ取り組みを数多く行っていくだけでは成果に繋がらないと感じていました。PDCAサイクルを続けていくことの必要性を強く感じました。
運動機会の促進
-
- 期間
- 2017年10月~現在継続中
-
- 取組内容
- 事務職のデスクワークや営業職の運転による座位行動が長時間にわたっており、健康リスクが高い為、運動機会の増進に取り組んでいます。
①社外リソースの活用
津島市ボランティアの方と共同し体操やストレッチを行っています。
社員全員で、あいち健康プラザ「生活習慣病を予防したい方向けのコース」に参加しました。
②オフィス環境の整備
・健康を基盤とした日常構築を考え、オフィスの20個余りのごみ箱をすべて撤去し1つにすることにより、「運動機会の増進・健康リスクの対処」を提案しました。
・集中力の低下や腰痛予防、気分転換や健康意識の向上を兼ねて、昇降テーブルを設置しました。
・オフィスチェアの代わりにバランスボールを導入することで、自然と体幹が鍛えられ、姿勢の改善や肩こり・腰痛の軽減が期待できます。 さらに、デスクワーク中心の生活で不足しがちな運動を、業務中に無理なくバランスを取り入れることができます。
③意識改革ウオーキングラリー
チーム対抗でウォーキングラリーを開催しています。
-
- 取組に対する成果
- ・あいち健康プラザでの研修終了後にアンケートを実施したところ、参加者全員が今回の研修に満足したと回答しました。「今後も健康について考えようと思ったか?」という問いに対しては、90%が「そう思う」と回答し、社員の健康意識向上が数値となって表れました。
・ゴミ箱撤去当初は、不満の声もありましたが、徐々にその環境が当たり前になり健康意識が向上しました。更に、リサイクルできる用紙をゴミ箱に捨てる社員がいなくなり、環境問題も改善されました。
・日々のバランスボールでの体幹を鍛えることにより、健康診断の結果で腹囲が減少した社員や、バランスボールを活用した運動動画をすることで社員が楽しく運動する様子が見受けられ、コミュニケーションの増進の機会となりました。
・チームによるインセンティブを設けたことで、「チームに貢献します」と率先して歩く社員が増加しました。ラリー終了後もあいち健康プラスを導入したことにより、社内のウォーキングマシンを積極的に活用する社員が増えました。
-
- 工夫したところ
- ・運動機会を促進するためには、自身の体の現状を把握することが重要であると考え、あいち健康プラザまでマイクロバスで移動し「生活習慣病を予防したい方向けのコース」を実施しました。ヘルスリテラシー向上を目的として外部の専門家と連携したセミナーを行い、部署ごとの交流を深めるために、20代から80代までが安全に行える「ドッチビー大会」も取入れました。
・「ゴミを捨てに行くことが運動機会の促進に繋がる」と伝えても全員が行動を変えるとは限らないからこそ、朝礼でプレゼンテーションをすることによって、作業効率の向上・健康リスク・廃棄物の発生防止などの効果があることを意識づけました。
・ウオーキングラリーを数年開催しましたが、その場限りの運動で終わっていた。運動機会を定着させるため、自発的に行動するきっかけを提供する『ナッジ手法』を用いました。モチベーションアップに繋げるには、適切に歩数を計測することが重要であるため、スマートウオッチを配布しました。また、インセンティブもチーム戦に変更しました。
他の企業等への健康経営の普及促進
-
- 期間
- 2017年10月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①自社ウェブサイトに健康経営のページを開設し、推進概要の詳細を説明することをはじめ、弊社の取り組む方向性を分かりやすく掲載しています。またブログコーナーも作成し、週に1・2度の頻度で取り組み事例の目的・内容を具体的に掲載してます。インスタグラムにも取り組みなどを掲載しています。業界新聞にも健康経営に取り組んでいる広告を掲載しました。
②お取引先様の経営者の方々から相談を受け『健康経営優良法人認定』取得のお手伝いをさせて頂きました。
③外部からも講演依頼を受けました。
弊社の、取り組みを始めてから今に至るまでのストーリーや、取り組み方を説明いたしました。
-
- 取組に対する成果
- ・経済産業省や全国健康保険協会、津島市のホームページや中部経済新聞社、協会けんぽと津島市役所の保健師からも掲載依頼がありました。また、ウェブサイトの掲載内容を読まれた企業から、取り組み内容や取り組む意味・成果等について取材を受けました。
・ブライト500の認定を受けて以来、20社以上の経営者の方々へ『健康経営』をするとどう変化するのか、どのように取り組むのか等、サポートさせて頂いている状況です。
・愛知県からオンデマンド配信を含むセミナーの講師依頼がありました。
その後、保険会社やEXPOでの動画配信依頼もあり、登壇させていただきました。500人以上の方にお伝えする機会に恵まれました。
津島市で優秀賞を5年連続受賞し「殿堂入り」の表彰をしていただきました。今年度は新聞社への掲載、過去には地元テレビ局が撮影する中、取組を発表いたしました。
-
- 工夫したところ
- ・弊社が健康経営の取り組みをスタートさせた当初は、何をどう取り組んでよいか、取り組む結果として企業・社員の健康にどう影響するのか、手探りの状態でした。そのことを踏まえ、他の企業の方の参考となるよう、また、それぞれの会社にフィットした内容で取り組むことができるよう、弊社ウェブサイトやブログに健康経営の取り組み内容の目的・詳細を具体的に記載しています。また、必ず写真も掲載し分かりやすくしています。
・週に一度、必ず健康に関するブログの掲載をしております。ブログの掲載のネタとして社内のヘルスリテラシーの向上や他企業への健康経営の取り組み事例として分かりやすいよう、写真を多く使用をしています。
・講演に登壇する際は、受講された方にとって理解しやすく、心動かされるスライドを準備するよう努めています。
受診勧奨の取組
-
- 期間
- 2017年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①全従業員の健康診断の受診予約
②受診状況を一覧表で管理しており、必ず受診するまでフォロー
③再検査対象者の受診予約
④再検査日を出勤日認定し、検査後は受診報告書を提出の徹底
⑤がん検診などの任意検診の受診も促しています。
健康診断結果を集計・分析し、有所見率・BMI・腹囲などはグラフにしてデータ管理する。
-
- 取組に対する成果
- 健康診断の受診及び、有所見者に対する再検査について、フォロー体制を確立したため、全従業員が100%受診できています。更に、健診後の特定保健指導対象者の予約を経営管理部で行い、社内にて特定保健指導実地場所も提供しているため、実施率は100%です。2022年度から人間ドックの費用補助を周知したところ、35歳以上の人間ドックの受診率は88%になりました。
意識改革後、費用補助をすることによって、「これならやってみようかな・やっぱり受診した方がいいよね」という声が上がり受診の輪が広がりました。
-
- 工夫したところ
- 健康診断の受診について意識を高めるためにセミナーを行いました。
人間ドックの費用はクリニックによって違うため、費用・環境面を踏まえ何件か問い合わせをしています。それにより、会社・個人負担額の予算を検討しました。その結果、人間ドックの個人負担を4,000円とし、受診しやすい環境を作りました。オプション検査についても半額補助としています。健康診断の予定を社内カレンダーに掲載し、業務上の配慮ができるようにしています。
50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施
-
- 期間
- 2020年08月~現在継続中
-
- 取組内容
- 従業員のメンタルヘルス不調を防ぐためには、業務に関するストレスや不安を把握し、どんな要因が心理的な負荷になっているか把握する必要があるため、年に2回実施しています。気づきを促すことで、セルフケアにつなげています。外部に委託をして「オンライン産業医面談」、「健診管理サービス」、「オンライン医療相談」、「ストレスチェック」など、産業保健業務をサポートするオンラインサービスに加入して取り組みました。部署・年齢ごとに分析した後に、職場環境の改善に活用しています。
-
- 取組に対する成果
- 年に2回行う事によって、不調者に対して、サポートしていることが、本人の状況の変化につながっていることを適切に理解できました。仕事量の調整や、部署ごとのコミュニケーションの促進にもつながっています。
また、部署ごとの上長に教育の場を設けたことによって、適切なフォローにつながりました。
-
- 工夫したところ
- 健康経営推進チームがPDCAサイクルを回している中で、イベントにコミュニケーションの場をつくれるようにしました。部署で、不調者がいる場合は、配置換えをしたりして様子を見ています。
健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定
-
- 期間
- 2017年05月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・健康診断結果を性別・年齢・部位別に集計・分析して把握。
・ストレスチェックの結果をセクションごとに分析して把握。
・外部健康経営アドバイザーと定期的に対話をして目標を数値化。
・健康課題に対するアンケートを社内で年に2回実施し数値化し目標を設定。
・人事責任者が個人面談を通して把握。
-
- 取組に対する成果
- ・アンケートの結果、健康課題への意識も高まり食事改善を考えたりするものが増えた。
・運動の機会を社員同士で取り組むものが出てきました。
・メタボリック症候群が減りました。
-
- 工夫したところ
- ・外部健康経営アドバイザーとの対話を定期的に行い課題を把握し、課題を重視できる内容のセミナーを数回開催しています。
・保健師に健康診断の有所見者に対して、食生活などの保健指導を依頼しています。定期健康診断の有所見者を含むすべての社員に対して栄養改善・運動に取り組むよう教育セミナーを実施しています。定期健康診断全体の有所見者率・男女別・年齢別においても推移を出し、検査項目別の有所見者率をグラフ化し変化を観察し改善策を考えています。
産業医または保健師が健康保持・増進の立案・検討に関与
-
- 期間
- 2019年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- 保健師に、弊社に数回来訪していただき、状況を把握していただくようにしています。その後、社員一人ひとりに向き合えるよう、保健師と健康経営推進担当者が打ち合わせをしています。また、その内容を、健康経営責任者と経営層とで取り組み内容の報告と相談をしました。
-
- 取組に対する成果
- 保健師に定期健康診断から健康を保持するための提案をしていただくことにより、健診結果の見方や改善策などについての意義あるセミナーが開催できました。立案・検討に関与してくださる機会をつくることによって、専門家の目線は非常に大切だと感じました。
①健康運動指導士のアドバイスにより、自分自身の体の状態を把握した上で、将来の健康リスクを知り、何を取り組んだらよいかを知ることができた。理解したことによって、会社にある運動機器の活用頻度が増えました。
②歯科衛生士により、歯周病は健康リスクがあるという事を話していただいた。その後、昼食を終えた後に歯磨きをする人が25%増えました。
-
- 工夫したところ
- 健康保持・増進は、病気だけではないので、その他にも専門家と直接お話しする機会を作っています。
適切な働き方の実現
-
- 期間
- 2017年05月~現在継続中
-
- 取組内容
- 適切な働き方の見える化を図りました。申請もしやすく、社員全員が把握できるようDX化も図りました。
・残業時間の申告制度を設定し、紙媒体ではなく申請書はデータ管理にしました。
・ノー残業デーの設定をし、当日はお知らせチャットで全員が把握できるようにしました。
・年次休暇の取得を促進する取り組みとして、シートを作成しました。
・時間外労働の削減を管理職の評価項目に設定しました。
・従業員の働き方の改善を目的とした設備投資・システム導入をしました。
・個々のワークバランスを重視し働き方の希望に合わせた適切な配置転換をしました。
-
- 取組に対する成果
- ペーパーレス化をし、ソフトなどの導入と社員教育をすることにより効率化を図りました。
ノー残業デーを周知することにより、残業時間が平均34時間と23%減少しました。
個々のワークバランスを重視し働き方の希望に合わせた適切な配置転換をすることにより、家庭生活や自身のライフスタイルのバランスをとれる社員が増えました。
-
- 工夫したところ
- 紙媒体ではなく、データ管理することによって、社員が一人ひとり携帯しているiPhoneで確認でき、常に全員が把握できるようにしています。また、把握できると改善に至るまでの時間が短く、適切な働き方を維持できることにもつなげています。また、セクションごとに残業時間の平均値を出し、リーダーと経営層で改善策を検討しています。
コミュニケーションの促進
-
- 期間
- 2017年10月~現在継続中
-
- 取組内容
- コロナ禍前は毎年、社員全員参加にて海外旅行の企画や家族交流も含めたキャンプなどのイベント実施していました。忘年会では、プレゼントを用意したゲームを企画し、コミュニケーション促進に努めています。
コロナ禍では、社内で「ありがとう」を伝える『サンクスカード』を作成しました。
さらに、ゴルフサークルを設立し、敷地内にゴルフ練習場を設置しました。また、ゴルフクラブやゴルフボールを寄付し、就業前や就業後、お昼休憩中に自由に練習できる環境を整えました。
-
- 取組に対する成果
- サンクスカードは、思いもしない方から温かい言葉をもらえて喜んでいる社員も多くいました。ゴルフサークルは、先輩社員が、未経験者の後輩を教えてあげたりする光景は、微笑ましく、仕事とは別の顔で関係が縮まりました。会社の駐車場で、感染症対策を配慮したバーベキューは、家族の子供たちも来て賑わい、形を変えたコミュニケーションではありましたが、気持ちが通じ合う企画で社員同士の距離が縮まりました。
-
- 工夫したところ
- サンクスカードは、持って帰ってもらえるよう封筒を用意し、家族の方にも共感してもらえるよう説明し渡しました。日頃、仕事をしている姿を見ることができない家族にも、頑張っている姿を伝えることによって共感してもらえるよう取り組みました。
また、忘年会では、一人ひとりにメッセージを書いてもらい、音楽を挿入するなどストーリーにしたスライドショーを作成しました。
治療と仕事の両立支援
-
- 期間
- 2017年05月~現在継続中
-
- 取組内容
- ・勤務時間内に通院可能な環境整備。
・勤務時間・作業内容・就業上必要な対応の策定。
・病気の治療と仕事の両立に向けた面談の実施。
・復帰する部門の上司に対する両立支援の理解の促進。
・保険加入による治療費や休業補償などの金銭補助。
-
- 取組に対する成果
- 退院後、病気になりがちだった社員が両立を得たこの頃は健康を維持できています。
-
- 工夫したところ
- 退院後の社員のきめ細かな状況を把握しケアに努めています。
保健指導の実施
-
- 期間
- 2017年10月~現在継続中
-
- 取組内容
- 健康診断の当日、必要と判断された者には保健指導を実施しています。
従業員の特定保健指導受診のための勤務シフトの時間調整を行っています。
-
- 取組に対する成果
- 受診率は100%です。
-
- 工夫したところ
- 健康経営責任者がクリニックに直接予約し、社員が業務フォローを踏まえ、全員周知できるようカレンダーに記載しました。
食生活の改善
-
- 期間
- 2017年10月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①食事の質の改善
メタボリック症候群の方や朝食をとられない方の健康維持のために、ランチバイキングを実施しました。ランチバイキングは、30品目とる食事を意識して、有機野菜や高蛋白質の素材を使うなど食生活の意識改革をしました。
②健康を意識する『ヘルシーデー』を毎月1日に実施
ヨーグルトや果汁ゼリー・野菜ジュース・青汁などにて栄養バランスを意識できるよう、食生活の改善の情報と一緒に提供しました。
③食のカレンダーの活用による意識付け
大豆の日・ビタミンの日・プロティンの日・大腸を考える日・野菜の日と、もともと設定されている日を活用して、意識づけと摂取する効果を明記した内容をチャットで周知し、食品の提供(ビタミンの日には、カットしたオレンジ等)をしています。
-
- 取組に対する成果
- 自ら青汁を飲む社員が増えるなど意識が変化し、コンビニで購入していた方が手作り弁当を持参したり、メタボ予備群の方が野菜豊富なお弁当に切替えたりするなど、食生活の知識の向上が顕著に表れました。
また、社内自販機で、青汁やビタミンを意識するジュースを買う社員が増えたり、水分補給のためのマイボトル持参の社員が増えました。
-
- 工夫したところ
- 季節においての健康課題を取り入れたり、社会問題を把握し、健康課題のテーマを毎月決定することで、社員に身近になりヘルスリテラシーの向上にもつなげています。
禁煙対策
-
- 期間
- 2017年10月~現在継続中
-
- 取組内容
- 始めのころは、副流煙による健康リスク対策だけでしたが、現在は就業時間内だけでも喫煙者の健康リスクが高まらないように『敷地内・周辺禁煙』を決定しました。
①喫煙者補助食品の禁煙サポートとして、世界禁煙週間のポスターを貼り(禁煙者から喫煙者へのメッセージも掲載)、禁煙補助食品を配布。
②禁煙者には1年に1回『環境功績賞』として1万円を支給。
③禁煙にかかる費用補助をするとともに、クリニックに資料を依頼し、社員に配付。
④喫煙者へ『煙草の害による健康リスク』をテーマに1年に1回セミナーを実施。
-
- 取組に対する成果
- 喫煙者が禁煙するきっかけとなり、喫煙者が10%減少しました。また、健康を考えて禁煙できなくても本数を減らすなど努力する社員も増えてきました。
-
- 工夫したところ
- 喫煙者に海外のたばこのパッケージにもなっている写真、体にどれだけ害があるかを分かりやすい写真をメッセージカードと一緒に渡しています。健康を応援する仲間からの心温かいメッセージに、何かきっかけになってくれるよう考え出したのが始まりです。
従業員の感染症予防
-
- 期間
- 2017年10月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①社員と配偶者にインフルエンザ予防接種の費用補助をする制度を導入。
②感染症予防対策として空気清浄機をオフィス・食堂・会議室に設置。
エアコンにセッティングする空間除菌剤を全室に設置。
③オフィス・トイレなどすべての部屋にアルコール消毒液を設置。
④うがいできる場所の環境づくり。
⑤検温できるよう赤外線体温計を導入し、検温表を社内SNSにて管理・換気の徹底ディスタンスできる社内設備。
⑥マスクを社員と家族に配布するなど家族での感染に配慮。
-
- 取組に対する成果
- 出勤・外出後の手洗い・うがいをする事の効果を説明したことにより定着しました。空間除菌剤の導入や健康管理の仕方を説明したりしたことにより、今までインフルエンザ・風邪で休んでいた社員がゼロになりました。
また、新型コロナウィルス感染予防に関しては、以前から定着していたので、導入はしやすかったです。
-
- 工夫したところ
- インフルエンザの予防接種は、クリニックの予約も管理部で実施しています。その時間の業務の影響も部門ごとにフォロー体制を整えています。
また、朝礼で報告・社内チャットにて連絡するなど、一人ひとりに呼びかけ、感染予防に徹底しています。
長時間労働への対策
-
- 期間
- 2017年05月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①長時間労働者に対して、上司・人事担当者による面談
②長時間労働者に対して、産業医による面談や指導の実施
③長時間労働者の管理職に対して、人事担当者・経営者による面談
・個人の業務負荷を見直し、勤務時間を制限
④勤怠管理システムにて、残業時間が一定時間を超えた場合は該当の社員とその上長に対し、残業時間の通知
⑤業務の効率化を図るためのDX化の推進
⑥長時間労働することによる健康リスクの情報発信
-
- 取組に対する成果
- ・長時間労働者と上長・人事担当者が、面談を行うことにより長時間労働の原因の対策と改善について考える機会となり、本人の状況や上長の業務管理の把握を行うことができました。
・勤怠管理システムを導入することにより、自身の残業時間と管理者は部下の残業時間が数値としていつでも可視化できるため、定期的にブラッシュアップができ、業務の共有化や上長とのコミュニケーションが増えました。
・業務の効率化のために、DX化の推進も相まって、残業時間が平均34時間と23%減少しました。
-
- 工夫したところ
- ・勤怠管理システムにて、残業時間が一定を超えた場合は、アラート機能として長時間労働者とその管理者にメールで通知が来るよう設定を致しました。超過するアラートのの設定を細かく行うことにより、残業時間の管理を徹底して行うことができました。
・DX化の推進により、マニュアルを都度作成するなど
メンタルヘルス不調者への対応
-
- 期間
- 2017年10月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①メンタルヘルスに関する社内の相談窓口の設置・外部相談窓口の周知
②ストレスチェックの導入
・津島市のHPでのメンタルヘルスチェック「こころの体温計」の実施
③従業員と上司の1対1の個人面談を定期的な実施
・本人の状況を踏まえた配置転換などを配慮した働き方の改善。
・メンタルヘルス不調者と上長・人事責任者(必要に応じて社長)との定期的な面談。
④メンタルヘルス不調者の復帰と医師の意見を踏まえた支援体制づくり。
・疾患の再発、新しい問題の発生などの本人の状況把握。
⑤ハラスメント研修の実施
・カスタマーハラスメントに関する対策について明文化を行い、研修にて社内周知
-
- 取組に対する成果
- ・メンタルヘルスに関する外部の相談窓口について社内での相談窓口より、活用がしやすい環境を整備することができました。
・ストレスチェックの導入により、自身のメンタルヘルスについての理解を深める機会をつくりました。
・メンタルヘルス不調者の配置転換により不調を改善できました。
-
- 工夫したところ
- ・ストレスチェックの導入により、集団による定量的なデータを分析することができ、原因への対策や予測が可能となった。
・メンタルヘルス不調者の配置転換をし、本人の状況を把握できるよう環境整備し、不調者に対しての病気の理解と対応をどうするのが良いのか、経営層と人事担当者と上司で、話し合う機会を設けました。
女性の健康保持・増進に向けた取組
-
- 期間
- 2018年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- ①婦人科健診・検診の受診勧奨・受診しやすい環境づくり
婦人科健診・検診のオプションを会社が費用負担・有給の特別休暇付与を行っている。
②女性の健康課題に関する理解促進のためのセミナーの実施
やせ・冷え・のぼせ・PMS・更年期障害に関するセミナー・生理休暇の有給化・管理職の周知
③女性の健康専門の社内外相談窓口の設置(女性の健康づくり推進者の設置)
④女性専用の休憩室の設置。
⑤女性の健康を維持するためのツールの支給
・冷え対策としてブランケットの配布
・サプリメントや健康ジュースの支給
-
- 取組に対する成果
- ・婦人科健診・検診を嫌がる社員もいましたが、女性の健康維持をセミナーを通して受診する意味を伝えたところ、社員への理解も深まり、毎年全女性が社員受診を行っております。
・女性の健康課題に対するセミナーを行うことで、ヘルスリテラシーの向上を行うことができました。それにより予防対策ができました。
・女性専用の休憩室の設置により、プライベートに配慮した空間を提供することで、リラックススペースとなり生産性の向上を図ることができました。
-
- 工夫したところ
- ・婦人科健診・検診は、必要性を理解していないと避けたいものである気持ちも受け止め、受診する意味を伝え検診を受けるよう勧めました。現在は、女性のオプション検診の費用も会社負担に変更を致しました。
・セミナーの際には、実際に一日の摂取目標の設定や、自身のBMIの測定を行うことにより自身が健康改善する良い機会となりました。
・女性専用の休憩室がなく、設置には経費がかさむことも避けられないと思っていたところ、DIYで工夫して設置できる運びとなりました。