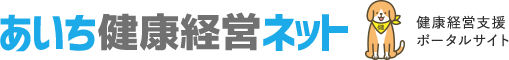医療法人全医会
イリョウホウジンゼンイカイ
- 101~300人
- 医療法人/サービス業
| 所在地 | 〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町高雄郷東41 |
|---|---|
| URL | https://www.itoortho.jp |
| 社員数 | 229名 |
| 業種 | 医療法人/サービス業 |
- 業務内容
- 全医会グループは、せぼね(脊椎)治療において、19,432件(14年間)の手術実績がある“せぼね(脊椎)専門の医師集団”です。全国より患者様にお越しいただいております。
身体の負担が少ない手術として数ミリから十数ミリの小さな切開で行うものを主としています。骨・筋肉・靭帯の切除を最小限にとどめ、神経・血管への接触をできる限り抑えます。お身体のご負担が少ないことから、入院期間が非常に短く(最短で1泊)、回復が早いため、普段のご生活やお仕事に早くお戻りになることができます。体力や筋力の低減を抑えることができ、特に高齢者の方にとっては重要なメリットであります。患者様の痛みをいち早く取り除くため、早期治療を目指し、この分野において臨床・学術ともに鋭意取り組んでおります。
健康経営に関する
自社のセールスポイント

医療機関として、職員の感染を防ぐためのワクチン接種や生活習慣病予防の特定保健指導など、以前から実施していたものもあります。健康経営の視点を持つことで働き方改革の一環として長時間労働の縮小と業務分担を柱に職員間のコミュニケーションを取りながら、各部署毎に施策を取っていただくことが出来ました。理事長、院長からのトップダウンを通し、全体の意識が「患者のため、自分のため、仲間のため」という当院のスローガンに向けて大きく改善しています。
一般相談窓口の周知、職員向け・管理者研修の場を大切に、今後も継続していくことで必要なコミュニケーションの取り方や未然にハラスメントを防ぐことも可能と考えます。職員数が増えてきてその分たくさんの意見もありますが、職員の声を聴くことに努め、当院で働けて良かったと言っていただけるような病院を目指します。
すべて開く閉じる
取組状況について
健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)の設定
-
- 期間
- 2023年04月~現在継続中
-
- 取組内容
- 長時間労働の減少を図るため各部署ごとの残業時間を把握し、業務量を減らすための対策を行う。
管理職において長時間労働の傾向が強いため、管理職が持っている業務量の書き出しと振り分けられる業務の把握、引継ぎを行う。
健康増進のために健診の受診率および、二次健診の受診率を100%になるよう衛生委員会にて周知・意識付けに関して取り組みを行う。
-
- 取組に対する成果
- 年を追うごとに残業時間は減っている状況になっているが、時期によっては変化が見られないこともある。
管理職の業務量の見直しは残業時間が減っていることから改善がみられていると考える。
健康診断の受診率は100%だが、二次健診受診率は2023年で82%だったが2024年は52%と低下しており、職員の意識改革のための取り組みが必要。
-
- 工夫したところ
- 長時間労働に関しては、各部署で状況が異なるため、管理職の会議にて取り組みについて周知してもらうことで全部署への周知が出来た。
健康診断は当院で実施しているため、受診勧奨への声掛けや健診を受けやすい環境に関しては配慮が出来るため、100%の受診率となっている。
管理職及び一般社員それぞれに対する教育
-
- 期間
- 2024年07月~現在継続中
-
- 取組内容
- 2024年はメンタルヘルスを重点目標として院長からの発信も含め、働きやすい職場にするために職員向けの労務士からの研修と管理職が知っておいてほしい内容の研修を愛知産業保健総合支援センターに依頼し、研修を実施した。
労務士からはコミュニケーションの取り方や伝え方、伝わり方、ハラスメントに該当していきそうと捉える内容について、と相談窓口の周知を45分間で実施。
管理者研修については傾聴の仕方やマインドフルネスの呼吸法の実践、ハラスメント判定となった過去事例を基にグループワークをし、出た意見を発表して頂いた。
90分実施。
-
- 取組に対する成果
- 2024年のストレスチェックからコミュニケーションに関しては改善が見られるので効果があったと考える。
管理者研修ではアンケート集計を行い、感じたことや今後の研修への希望について等の内容を把握した。知っている内容もあったとの回答も多かったが、意識付けとして継続していくことの必要性を感じたという意見が最も多かった。
メンタルヘルスにおいて管理者の対応がハラスメントになったり、部下の不調をいち早く察知し、解決するために必要な適切な対応がなされるよう今後も継続していく。
-
- 工夫したところ
- 経営者を巻き込んだことで優位に話し合いができた。
メンタルヘルス不調者への対応
-
- 期間
- 2021年12月~現在継続中
-
- 取組内容
- 衛生委員会において、メンタルヘルスの体制について協議。年に数人休職者がいるため、業務担当の振り分けを行なっている。事務には、休職する場合の手続きについてのフローチャートを作成依頼。メンタル不調者への適時面談等は、産業医に一任している。
-
- 取組に対する成果
- 産業医面談も含め、一般相談窓口を設置。一般相談窓口と産業医相談のフローチャートを作成、各部署に掲示。
2024年の一般相談窓口の件数は年9件、産業医面談に移行した件数が5件、直接、産業医面談に行かれた件数は0件である。
今までは各部署の所属長しか相談する場がなかったことや所属長から部下の面談をしてほしいとの依頼もあるため、今後も継続する。
-
- 工夫したところ
- フローチャートの作成にあたり、衛生委員会での意見も聴取して何回かやり直しを実施。その分、分かりやすいフローチャートの作成が出来た。
受診勧奨の取組
-
- 期間
- 2021年08月~現在継続中
-
- 取組内容
- 衛生管理者から健康診断の結果を産業医に提出し、二次検査・治療が必要とされた者に対する受診勧奨と、結果記入表を衛生管理者から手渡しする。11月に未受診者への働きかけも実施。それでも未実施の者には、産業医から直接受診勧奨の実施。
産業医の変更により産業医から直接の受診勧奨はなされないが、衛生委員会の委員により各部署への受診勧奨を実施。
また今までは文書の提出を健診部に持参して頂くようお伝えしていたが、2024年から勧奨文書にQRコードを添付し、持参する時間を減らすような働き方を実施。
-
- 取組に対する成果
- 11月の時点では4割の提出状況であったが、12月時点で9割の提出あり。2021年度からの初めての取り組みであったが、衛生管理者と産業医が健診の事後フォローまで取り組み、健康管理が必要な人への働きかけが出来て受診に繋がった者が3割もいた。生活習慣病を悪化させないための意識付けが出来たことは良かった。
2023年に産業医が変わり、産業医からの直接の勧奨は無くなったが、委員会の仕事として各部署の委員がしっかりと働きかけを実施してくれたことは効果があると考える。しかし、2023年に82%だった報告数が、QRコードを入れた2024年では52%に低下したことから低下した背景を調べる必要がある。
-
- 工夫したところ
- 衛生管理者と産業医との連絡体制を心掛け、報告・連絡・相談を行なったこと。
衛生委員会の取り組みと位置づけたことにより各部署の委員が働きかけやすくなった。
産業医または保健師が健康保持・増進の立案・検討に関与
-
- 期間
- 2021年08月~現在継続中
-
- 取組内容
- 衛生委員会を軸に、職員の健診結果の把握やストレスチェック結果の把握など、産業医と保健師との連携を取っている。3月からは産業医の職場巡視も開始し、職場環境への調査も実施中。巡視で出た意見は管理部へ報告。対応を依頼する。
働きやすい職場で健康を保持・増進するために必要と考える重点項目を軸に新しい取り組みも踏まえ、実践している。
-
- 取組に対する成果
- 特にストレスチェックの結果から、ハイリスク部署に関して保健師の面談を実施。
2023年度は特に従業員間のコミュニケーションが取れていないことから院長と相談し、院長から職員に伝えることで2024年の結果は改善が見られた。
2024年の委員会としてもメンタルヘルスを重点目標とし。管理部も交えながら全職員向けの研修として当院の労務士から働きやすい職場について講話して頂き、1カ月後には管理者研修としてワークも含めた実戦形式での研修を実施した。
-
- 工夫したところ
- 院長から伝えるトップダウン方式を用いることで、早い改善に繋げることが出来た。
研修を行うにあたり、日時の設定であったり研修委員会にも配慮をして頂いたことで時間の確保が出来た。管理者研修においては日々忙しい中時間を作っていただくために病院休診日を確保し、管理部から所属長へ伝えて頂いた。管理者研修の参加率は100%、アンケートの返信も100%なので意識は高いと考えられる。
適切な働き方の実現
-
- 期間
- 2021年11月~現在継続中
-
- 取組内容
- 残業時間の管理・削減に向けての取組は、以前から事業所側から報告・注意という形で実施しており年々改善されてきてはいるが、一部の特定のスタッフは残業が多いため、残業が多いスタッフの業務量の把握・改善計画立案を、2022年度の取組課題に位置づけている。
残業時間を確認すると管理者の残業時間が多いことから業務内容の振り分けを管理部、看護部を中心に実施。
有給消化率アップのために研修日での全体周知を実施。
法定を超える子育て・介護のため等の短時間勤務を可能としている。
-
- 取組に対する成果
- 年を追うごとに残業時間は減っている状況になっているが、時期によっては変化が見られないこともある。
管理職の業務量の見直しは残業時間が減っていることから改善がみられていると考える。
有給消化率は部署によって大きく変わるが2023年1月~12月で66%~100%。
短時間勤務においては相談があった場合、速やかに部署も交え短時間勤務が出来るよう配慮している。
-
- 工夫したところ
- 長時間労働に関しては、各部署で状況が異なるため、管理職の会議にて取り組みについて周知してもらうことで全部署への周知が出来た。
研修日で有休取得についての話が出ていることから有給消化については
理解している。部署により相談しながら有給の取得が出来ている。
保健指導の実施
-
- 期間
- 2017年06月~現在継続中
-
- 取組内容
- 職員に関しては当院保健師から保健指導の案内をし、強い拒否者を除き毎年実施している。
2024年から健診中の待ち時間を利用し、特定保健指導を実施。健診中に声掛けをすることで全員に声掛けが出来、保健指導の初回面接が終了できる。
今までは後日に実施していたため、時間の確保のために所属長への許可も必要だったが、健診の待ち時間を有効活用できるようになった。
-
- 取組に対する成果
- 健診の待ち時間を利用したことで100%の実施率が達成できた。
本人からも事後ではなく、健診中に実施出来ることは好意的に捉えられる発言も多かった。
-
- 工夫したところ
- 健診の待ち時間を利用したことで100%の実施率が達成できた。
従業員の感染症予防
-
- 期間
- 2010年02月~現在継続中
-
- 取組内容
- 当院にて、B型肝炎・インフルエンザ・コロナワクチン接種を実施。インフルエンザワクチン接種については、同居する家族も対象に実施している。2021年度より、血液を扱う部署のみに実施していたB型肝炎ワクチン接種を、全職員接種へと規模を拡大した。
-
- 取組に対する成果
- B型肝炎ワクチンについては健診にて抗体価を確認し、感染委員会において実施し、対象者の9割が接種済み。抗体が付きにくい方に関しては、本人の意思を尊重。
-
- 工夫したところ
- 案内は感染委員が実施。内科にて接種を行なうため、内科に職員一覧と希望の有無欄の用紙を渡す。返答がない職員には内科から感染委員に連絡し、周知を図っている。
長時間労働への対策
-
- 期間
- 2021年03月~現在継続中
-
- 取組内容
- 残業時間の管理・削減に向けての取組は、以前から事業所側から報告・注意という形で実施しており年々改善されてきてはいるが、一部の特定のスタッフは残業が多いため、残業が多いスタッフの業務量の把握・改善計画立案を、2022年度の取組課題に位置づけている。
2021年から2024年まで、年々残業時間は改善されてきている。管理者に関して残業時間が多くなる時期が見られるが年度の切り替わり時期でもあり入職者も多い時期のため経過を見ていく必要がある。
-
- 取組に対する成果
- 年を追うごとに残業時間は減っている状況になっているが、時期によっては変化が見られないこともある。
管理職の業務量の見直しは残業時間が減っていることから改善がみられていると考える。
-
- 工夫したところ
- 長時間労働に関しては、各部署で状況が異なるため、管理職の会議にて取り組みについて周知してもらうことで全部署への周知が出来た。